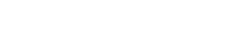“サーフィン発祥の地”で歴史を刻む
5月18日。千葉県いすみ市の太東駅から太平洋岸が近づくにつれて、景観が水田地帯から徐々に変化していく。アパートの傍らには、サーフボードキャリアの付いた自転車が置かれ、軒先では、ウェットスーツ姿の女性が休憩を取っていた。海岸入口の前を走る幹線道路『外房黒潮ライン』沿いには、サーフショップや、外壁を派手にペイントした飲食店が目に付く。
ここ、『太東ビーチ』は、湘南(神奈川県)、鴨川(千葉県)と並び、“日本のサーフィン発祥の地”とも言われる、国内有数のサーフスポットだ。2020年東京オリンピックでサーフィン種目が開催される『釣ヶ崎海岸』(長生郡一宮町)も近い。
この日開催された『アダプティブ・サーフィン エキシビジョンマッチ』は、国内初の障がい者サーフィンの競技会である。JASO(一般社団法人日本障がい者サーフィン協会)代表理事の阿出川輝雄氏らが、昨年11月30日から12月3日まで米国・南カリフォルニアのラホヤで開催されたアダプティブ・サーフィン世界選手権『STANCE ISA WORLD ADAPTIVE SURFING CHAMPIONSHIP』を視察。現地の運営者から得た知見を元に協会を設立し、今回の大会の開催にこぎつけた。

海岸に到着すると、『JASO』の横断幕が張られたテントを中心に、Tシャツに短パン姿の男女が慌ただしく動き回る。駐車場とビーチの間にある段差にはスロープがかけられ、選手がビーチまでの移動に使う車いすと、競技時に選手を波打ち際まで運ぶバギータイプの車いすをそれぞれ1台用意。競技時には選手をサポートするボランティアが帯同し、医師、看護師も待機する体制が整えられていた。


“アダプティブ”という言葉の意義
“アダプティブ”は「適合性のある」と訳される。障がいを持っていても、創意工夫で可能性は広がる――。 “障害(Disability)”や“不可能(Impossible)”といった後ろ向きなニュアンスではなく、進歩的な意志を、この言葉から感じ取ることができる。障がい者スポーツを『アダプティブ・スポーツ』と呼ぶ米国では浸透する理念でもある。
「“アダプティブ”という言葉に対して、『あ、良い言葉だな』と。その大会がアメリカであるのを知って観に行ってみたら、非常に(雰囲気が)明るいんですよね。選手も26ヶ国から来ていて。日本はサーフィンがかなり進んでいる国なのに、(障がい者サーフィンの)協会も無かった。現地の人からも、『日本もこういう組織を作らないと』と言われて」
とは阿出川代表理事の言葉である。氏は、日本にサーフィン文化の根付いていなかった1960年代から普及に取り組んできた元プロサーファー。60歳の頃、脳内出血により右半身不随になり、一時期波から遠ざかったものの、サーフィンへの想いが消えることはなかった。この日も、選手の1人として波に乗る。

躊躇した出場。「楽しくできれば」と参加へ
13時の競技開始が近づくと、選手たちがビーチに集まり、各自のボードが並べられた。出場者は8名。阿出川代表理事を含めて、事前にエントリーのあった6名に加えて、2名が飛び入り参加。敷居を設けず、楽しむこと。エキシビジョンマッチならではの光景だ。
茨城県から参加した髙塚康之さん(42)は、20年程前にバイク事故で右脚膝上を切断し、義足を使用している。以前からサーフィンには取り組んでいたものの、義足の故障の為、1年程ブランクがあった。
「自分のレベルが低いから、本当は(出場を)躊躇したんですけど、障がい者でもサーフィンにチャレンジしていることを広める為に、楽しくできれば良いということで、参加の決意をしました」と話す。

この日、髙塚さんの使用していた義足は、ガムテープで補修されていた。「どうしても細かい砂が入ってしまう」と頭をかく。『膝継手』と呼ばれる膝関節部位の機構はデリケートで、砂が入ると正常に機能しなくなることも多い。「(今日のサーフィンで)確実に壊れます。ここ(膝継手)の部品だけでスペアを3個ぐらい用意しまして(笑)。壊れたら取り替えですね」
波打ち際からの声援に、思い思いのスタイルで
競技は全3回。まず、『HEAT』と呼ばれる予選ラウンドが2組行われ、試技点数で上位の4名がファイナルラウンドに進出する。通常、アダプティブ・サーフィンは障がいに応じてボードの乗り方が6カテゴリに分けられているが、今大会では特別ルールを適用し、クラス分けではなく、ハンディキャップ制度を導入してのジャッジ(試技判定)が行われた。
米国・カリフォルニア出身のサーファー、スケーター、シェイパー(サーフボードを削る職人)であるBen Wei氏のアナウンスと共に競技が進行する。
競技開始のブザーと共に、選手たちは自らボードを抱えて歩き、あるいはバギータイプの車いすで海へと乗り出して行く。今大会では、各回約20分の試技時間の間は、何度でもトライ可能というルールだ。

海上では、各選手が思い思いのスタイルで波に乗った。ボード前方部に装着されたグリップを掴み、腹臥位(ふくがい=うつ伏せ)でライディングを行う選手、義足側の脚をコントロールしながらスタンディング(立位)にチャレンジする選手。スタンディングに成功すると、ビーチからたちまち拍手が沸き起こった。
観客や報道陣は波打ち際まで寄り、ボランティアのサポートのもと、選手が波に遊ぶ様子を眺める。時に声援や拍手を送り、カメラを向ける。後方のテントからは、レゲエ・ミュージックが流れ、穏やかな雰囲気で試技は進行した。

「『割とできるでしょ?』というのを表現したかった」
千葉県習志野市から出場した長谷川義行さん(58)は、競技を終えて陸に上がると、他の選手と笑顔で握手を交わした。サーフィンを始めて5年。膝上切断の為、大腿義足を使用しているが、当初は義足を付けずに海に入っていたという。
「義足でサーフィンをしている人の映像を探していたら、海外の女の子が上手い具合に大きな波でスタンディングしてるんです。自分と同じ右脚の大腿義足。それを見て、『やっぱり立たなきゃダメだな』と。そこで海に入る為の義足を作って、スタンディング形式で始めたんです」

膝折れによる転倒を防ぐなどの理由から、サーフィンをする時は義足の膝継手をロックし、膝が曲がらない状態にする。その為、まず健足(義足では無い脚)で立ち、バランスを取りながら義足側のポジションを調整し、スタンディングの姿勢へと移行していく。「でも、体制が整う前に大体海に落ちてしまう。なかなか、思うようにいかないですよね」と苦笑い。
サーフィンで使用する義足と日常生活で使用する義足は別にしているという。「海水に浸けたらダメになってしまうので、義肢装具士さんからは、『基本的に義足で海に入るのはダメですよ』と。でも、この義足も義肢装具士さんの理解があって作って貰えた。その意味で、サポートあってのものなんです」
この日最も長時間のスタンディングに成功していたのは山本力也さん(46)。左脚の膝下が義足だ。乗り方のコツを尋ねると、下腿義足ならではの身体感覚で話してくれた。
「膝で足裏の感覚を持っているような感じ。僕のボードは真ん中にオレンジの線が貼ってあるので、テイクオフした時にボードをチラッと見て、その線めがけて自分の軸足を置くというトレーニングをずっとしている。体重がかかった時にボードが微妙に動くので、その変化を読み取ってボードコントロールを行っています」

「今回は“エキシビション”だから、アピールする場。(障がいがあっても)『割とできるでしょ?』というのを表現したかった」と山本さんは言う。
「『障がい者サーフィン』と日本語で言っちゃうと、何となく堅苦しかったり、ちょっと閉鎖的だから、言い方や表現の仕方を変えたい、と。競技でもあり、評価も付くものだけれど、1つの文化として、皆で楽しんで切磋琢磨していければ」

“水”と“裸”と“冒険心”
今大会では、有志で多くのボランティア・スタッフが駆けつけ、運営をサポートしたが、その中には3人のプロサーファーが含まれていた。田岡なつみさん(23)もその一人。幼い頃からずっとこの『太東ビーチ』でサーフィンをしているという。
「これまでも障がい者サーフィンにはボランティアで参加したことがあったけど、大会形式での実施は今回が初めて。障がいがあっても、サーフィンの魅力を色んな人に知ってもらいたいし、ぜひ体験してもらいたいと思っています」

2020年のオリンピックではサーフィンが正式種目として実施予定だが、パラリンピックでは種目採用には至っていない。阿出川代表理事は、2024年のパリ・パラリンピックでの採用に寄与すべく、活動を続けていく。9月にも同じ千葉県で大会を開催する予定だという。
「サーフィンは、“水”と“裸”。水と肌が触れ合う水泳のようなものに、“冒険心”が加わったサーフィンを、パラリンピックの場に取り上げて欲しい。そう思ってるんですよね」
阿出川代表理事は、柔和な笑顔で話した。


(写真:大石智久、吉田直人 校正・佐々木延江)