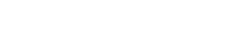アジア初となった旭川でのIPC(国際パラリンピック委員会)クロスカントリースキーワールドカップは、2月19日に7日間の全日程を無事に終了。閉会式後に行なわれた、さよならパーティでは、各国の選手、競技スタッフから、組織委員会、ボランティアに対して大きな感謝の言葉が述べられた。
大会の主催は、地元のスキー、障害者スポーツ、文化、観光などを目的とする市民団体による「2015 IPCクロスカントリースキーワールドカップ旭川大会組織委員会」で、障害のある人や、海外からの参加者を招いた国際的なスキー大会の経験がある。彼らが、98年・長野パラリンピック以降の日本で初の障害者クロスカントリースキーの国際大会を実現した。実際の大会運営にどのように取り組んだか。

「旭川らしさをイメージしたかった」と、大会セクレタリー(庶務)をつとめた、成田知樹さんは、すべての準備をほぼ終えた大会前日に話してくれた。当初、競技やセレモニーなど、時間のゆとりあるスケジュールを組んでいた。高齢者や、障害のある子供たちが、様々な場面で大会ボランティアとして参加したが、彼らが無理なく、工夫して取り組めるよう配慮したものだろう。
しかし、大会を主導するIPC側の要求は、この提案に対し「スピーディに」ということで、地元の競技スタッフとIPCスタッフの間に乖離したイメージがあった。
今大会の競技進行を決定するのは、ロシア人のTD(テクニカル・デリゲイト)ゲオルギー・カディコフ(Georgy Kadykov)氏を中心とした、IPC側のルールを遂行する審判チームで、組織委員会側の進行を代表して行なう成田さんは、要求を満たしつつ、旭川らしさを発揮するにはどうしたらいいか、各担当との調整に奔走した。

成田さんら、日本人競技スタッフの対応に対して、ゲオルギー・カディコフ氏は、さよならパーティでコメントをくれた。
「2006年のバーサーロペットを経験し、旭川が日本のクロスカントリーの中心地だということは知っていたが、初めての開催で、IPCの大会として、いくつか問題があると思っていた。しかし、着いてみて、驚いたのは、準備がすべて整っていたことだ。大会バックアップ、宿泊、食事、人々の出会いと交流の場が、すでに準備されていた。
通常、事前にジュリーメンバーと組織委員会は話し合い、要求に沿っているか、調査をする。その要求リストは、世界中の全ての組織委員会がクリアできるわけではない。旭川では、富沢のコース係の皆さん、ボランティアまで、要求は満たされた。スタジアム、コース、セレモニーの内容も含めて。さらに、私たちの意向を聞くことも忘れなかった」
また、カディコフ氏は、「個人的には、旭川らしさとIPCの意識のずれはあると思います。組織委員のみなさんが目指していたのは、確かに重要なことだ。アジア人の文化、日本人の文化、気持ちが穏やかとは聞いていたが、それは今回、表情やふるまいから感じ取ることができた。しかし、当初、意識のずれはあった」と話した。
たとえば、日々のコース準備は真夜中の作業だったが、あらかじめ決められた、スタンディング、シッティング、男・女のそれぞれのコースレイアウトに加え、TDによるコース整備や変更の指示があり、結果的に競技開始前まで調整が行なわれた。
「コース係の方は、毎日圧雪はしていましたが、スタートする時刻に意識のずれがあった。圧雪は降雪確率が20%でもする。雪が降れば、その都度圧雪する。コース変更も、安全上の理由を考慮している。やっていくうちに理解し合い、お互い学びあったと感じている」と、話してくれた。

今後の旭川での大会に希望することとして、カディコフ氏は、「バイアスロンの会場がほしい。そして、ここ旭川で、日立やソニーなど日本のデジタル技術を投入し、電光掲示板やスタンド、雪中に設置できる計測用のセンサーも設置したい。多くの観客、ブラスバンドの演奏、生中継など、ノルディックの世界選手権を旭川で開催したい!」と話していた。
放送を担当した今野征大さん(北海道雨竜高等養護学校)は、日頃から旭川らしさを大切にするスタッフのひとり。知的障害のある学生ボランティアとの放送局の運営に加え、メダルセレモニーの進行も努めた。これまでも場内放送では、選手のプロフィールやパラリンピックでの活躍を紹介するMCで会場を盛り上げていたが、IPCルールの今大会では英語での放送がメインとなる。今野さんは、地元のファンを増やす重要性から、英語と日本語の放送を行ない、合間に、いつもの楽しいMCを取り入れ、選手情報、応援団長・ニッポンマンの様子を多くの観客に伝えた。また、アジアで初のワールドカップ、日本を代表する雪国・旭川を印象づける選曲で演出した。
こうして、9カ国から53名の選手を含む約100名の選手団を、地元の約100名の大会組織委員と200名を超える地元を中心とした市民ボランティアが、レース・練習・滞在を支えた。また30社・約80名になるメディアが大会を報じた。大会期間を通じて、自然の雪質やコース整備の状態によるレースへの集中力の高まりがあり、地元ボランティアの素朴で優しい歓迎ムード、居心地の良さが、旭川大会の成功のかぎになったようだ。