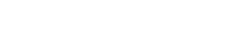パラフォト代表として、2004年アテネ大会から成田さんを取材し続けてきた一記者として、今は、彼女が天国で最も大切な友でありライバルだったドイツのカイ・エスペンハイン(Kay Espenhayn)と再会していることを祈ります。

誰も超えられない金字塔
日本パラリンピック委員会の河合純一会長(元パラ水泳日本代表選手、日本パラ水泳連盟会長)は、成田さんの訃報に接し、次のように語った。
「パラリンピックがまだメジャーになる以前から、共に高め合ってきた同志でした。彼女の功績は未だに誰も超えることができない金字塔です。4年前の東京大会まで現役で泳ぎ続け、誰よりも水泳を楽しんでいた姿が思い出されます」
その河合さんのアテネ後の著書「夢への努力は今しかない」(2004年)の推薦文で、成田さんは「河合くんは私に勇気をくれた。特別ではなく、普通に、自然に、生きる姿勢に感動できます」とエールを送った。お互いを励まし合う二人の姿は現在のパラ水泳チームの文化に大きく貢献している。
水の女王
成田さんは、アトランタから東京まで6大会に出場。金メダル15個を含む20個のメダルを獲得。2004年アテネ大会では1大会7冠という偉業を成し遂げ、「水の女王」と呼ばれるにふさわしい存在となった。
川崎で生まれ育ち、13歳で脊髄炎を発症し下半身まひで車いす生活となった成田さんが水泳を始めたのは23歳。横浜サクラスイミングスクール(横浜市青葉区)を拠点に練習を積み重ねた。

小学校の体育館で講演したときのこと、水泳を始めるきっかけについて、「仙台で大会があると聞いて、牛タンと新幹線に惹かれただけ」と明かし、ベテランは子どもたちの水泳へのハードルを軽やかに下げた。最初は「嫌いだった水泳」が、いまは(喋るだけでも)こんなに楽しいと、競技引退後の人生も水泳を中心とする人生を語る成田さんがまぶしかった。
成田さんにとって水の中は「自由になれる居場所」、であると同時に、厳しい練習の場でもあった。
成田さんは過酷なトレーニングと自らを追い込み続ける姿勢に「誇りがあった」と語っていた。「練習は楽しくない。苦しいです」「でも、楽しかったら競技者の誇りもない」という言葉に、トップを泳ぎ続ける成田さんの思いが凝縮されている。
永遠の友情 ― カイ・エスペンハインとの絆
成田さんの競技人生を語る上で欠かせない存在が、ドイツのライバルであり親友のカイ・エスペンハインである。アトランタ大会で出会い、互いを高め合った二人だったが、カイは2002年に病で34歳の若さで逝去した。
「カイの分まで泳ぐ」――その誓いが、成田さんを支え続けた。アテネ大会で7冠を達成した後、成田さんはドイツを訪ね、ライバルの墓前に金メダルを捧げた。
試練と復活
北京大会(2008年)のクラス分けが変更となり、より障害の軽いクラスでの勝負を強いられることになったことは辛いことだったと思う。練習の成果で記録を伸ばした結果の評価だった。北京では一つもメダルを取れないまま大会を終えた。パラリンピックのクラス分けの厳しさを知った。

北京のレースを終えた成田さんは、「”棄権してもいい”と言われましたが、その選択肢は全くありません。ここまできて、泳げる環境にありながら棄権した方がよっぽど後悔します。泳ぎ続けて、4年に一度のパラリンピックに出場して、自分がこの場で泳げる、ということが大切。水泳が好きなんです」と語っていた。
そして、「パラの前にはいつもいろいろなことが起こりますけれども、4年間みっちり練習したい」と、新たなクラスでのチャレンジを楽しむ姿は大いに後輩スイマーへのメッセージにもなると感じた。クラス分けのスポーツの厳しさとパラ水泳の醍醐味、身体を動かすことの可能性、スポーツの楽しさを目の当たりにした。
ラストレース、女子50m背泳ぎ(S5)で6位入賞
しかし、2012年のロンドン大会はアスリートではなくテレビの解説者として成田さんは取材側にいた。2014年に東京2020大会組織委員会理事に就任と同時に現役復帰を果たした。「泳ぐことで貢献することが一番だと思った」とモラトリアムを経てプールに帰ってきた。
51歳で迎えた2021年東京大会がラストレースとなった。女子50m背泳ぎ(S5)で6位入賞を飾り、「最後だからもう行ってこいと送り出してもらえた。本当に幸せな気持ち」と語った姿は、有終の美を飾るものだった。

最後に成田さんとお会いしたのは、2024年6月、パリ大会前の横浜国際プールでのことだった。地元の後輩・川渕大耀を取材に訪れた成田さんと、地元・横浜のプール再整備問題について初めて意見を交わした。あの真剣な眼差しと柔らかな笑顔が今も心に残っている。その後、細かなメッセージのやりとりがあったが、今年5月が最後となった。
遺されたもの
成田さんは、生涯を通じて「パラスポーツを通じて社会を変える」ことを願い語っていた。
「スロープやエレベーターだけでなく『心からの意識』が重要」
この言葉は、バリアフリーの本質を突き、私たちパラフォトが掲げる「パラスポーツのまちづくり」にも示唆を与えてくれた。

また、近年の若手へとバトンをつなぐ姿勢は、一人のアスリートだった頃の成田さんよりも、NPOメディアの記者としてより距離が近づいた思いがしていた。
由井真緒里が200m自由形で長年、成田さんが保持していた日本記録を更新した際、「母を超えるような心境」と語ったことは、その象徴だった。成田さんは、自らの背中を追う次の世代が記録を塗り替えることを心から喜び、誇りに思っていた。
成田真由美さん。もう天国でカイと再会し、再び泳ぎ、語り合っているでしょうか?
これからも成田さんとの出会いを胸に、パラスポーツを通じた社会変革、まちづくりに向けて、ともに歩み続けていけたらと思います。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。
(校正・小泉耕平)