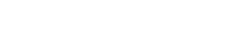デフリンピック100年の歴史と「伝えること」の意味
デフリンピック(Deaflympics)は聴覚障害(ろう)者のオリンピックで、1924年パリで第1回大会が開催され、昨年100年を迎えパラスポーツの国際大会としてパラリンピックよりも長い歴史がある。IOC(国際オリンピック委員会)との連携はあるものの共催関係ではない。伝統的にろう当事者による自律的な運営が行われており、手話や「ろう文化」といったアイデンティティの尊重と保護が国際的にも認められている。スポーツを通じて「誰もが平等である」ことを伝える場として、デフリンピックは独自の価値を持つ。
東京2020パラリンピックを取材したメディアとして、今回のセミナーで登壇者の話を聞く中で、東京2025デフリンピックが「お金をかけない大会」として目指す、“スポーツ本来の魅力発信”への意気込みが伝わってきた。パラスポーツのファンとして、そして報道する立場としても、自分たちの取材のあり方を改めて見直す機会となった。
スポーツは、誰もが個性を活かせる「共生の場」

冒頭、全日本ろうあ連盟の久松三二・常任理事は、デフリンピックの理念について次のように語った。
「デフスポーツの魅力や価値を伝え、人々や社会をつなぐ」「誰もが個性を生かし力を発揮できる共生社会の実現」
久松氏は、デフリンピックを単なる国際スポーツ大会としてではなく、社会における多様な人々のあり方を育み、つなぐ「装置」としての意義を示した。この認識は、従来のパラスポーツにおけるインクルーシブな取り組みをさらに進めるものといえる。
また、久松氏は3月から始まった全国キャラバン活動で自治体の手話言語の普及活動などと共に「デフスポーツ」と「ろう文化」の魅力を広く伝える取り組みに力を注いでいる。それは単にスポーツ大会の“観戦者”を増やすためではなく、“理解者”を育てる試みである。
音のない世界をどう「伝える」か──テクノロジーの挑戦

「音で伝えられないことを、光や文字、振動で届ける」
その言葉どおり、音声による案内が使えない場面でも情報が伝わるよう、透明ディスプレイ(例:https://kotobal.konicaminolta.jp/)、振動スピーカー、スマートグラスを活用した実証実験が進行中だ。これらの技術は、聞こえる人々に新たな“応援体験”をもたらす。
とくに「サインエール」は、手話の拍手をベースにして身体で伝える視覚的な応援スタイルで、デフアスリートに届ける新たな応援文化となるだろう。
「競技の背景を知ることで、観戦は応援に変わる」6万人の子どもたちに“知る観戦”を──事前学習が応援を生む
デフリンピックでは、6万人を超える児童・生徒が観戦を予定しており、それに先立って、デフスポーツや手話、聴覚障害について学ぶ授業が実施される。デフスポーツの価値・魅力や障害について学ぶことで、「ただ観戦する」から「ともに応援する」へ意識の変化が育まれる。
スポーツは競争であると同時に多様な立場が交流し、文化・歴史・社会・経済との関係性を育む場でもある。東京2020で試みられたリバース・エデュケーション(子どもたちが学び、家族連れでの現地観戦を促す)はコロナ禍により不発に終わったが、今度こそ、開催都市のスピリットが地域に根づくことが期待される。
出会いが交差する「デフリンピックスクエア」

代々木公園周辺に設けられる予定の「デフリンピックスクエア」は、大会の象徴になるエリアだ。
東京都スポーツ文化事業団準備運営本部の北島隆COOは、構想を次のように語った。
「練習会場、メディアセンター、文化体験の場を一体化し、人と人が交わる空間を目指す」
デフリンピックでは選手村を設けない。その代わり、選手は一般のホテルに宿泊し、自身の競技が終わればチームの応援や選手同士またはファンとの交流を楽しみ、東京・福島・静岡の地域を堪能することができる。
渋谷区代々木に計画されるデフリンピックスクエアには練習会場、記者会見会場、トランスポートハブ、文化プログラムなどを一体化したエリアが設けられる。選手村やオリンピックパーク的な要素をもつ交流と発信の中心地としての役割が期待される。
観戦無料──体育館から世界へ、スポーツの原点を見直す

東京都スポーツ文化事業団の板倉広泰・シニアマネージャーは、運営方針について次のように述べた。
「競技観戦は無料。中・小規模の体育館も積極的に使っていく」
「見たい人が自由に見られる」ことを保障する実践であり、地域と国際大会を直接結ぶ貴重な機会でもある。東京2020では実現しなかった「最高峰の競技の最前線の熱気」が、地方会場でも生まれる可能性に期待が高まる。
一方で東京オリンピック・パラリンピックの象徴だったメインスタジアムは残念ながら登場しない。
伝える自由と、つなぐ責任──メディアアクセスの課題
今回のプレスセミナーでは、「いつでも・どこでも・誰とでも」つながる大会を目指す意義が繰り返し語られた。UC(ユニバーサル・コミュニケーション)技術による視覚案内や、子どもたちへの事前学習など、情報の壁を越えて伝えようとする多様な試みが進められている。
一方で、メディアやクリエイターが「伝える」ための環境整備には課題が残されている。記者からは、手話通訳の音声使用、フォトポジションの確保、撮影者用ロッカーの設置などについて質問があがったが、現時点で準備は進んでいないという。
UCをコンセプトに、手話通訳や競技中の視覚的表現においては、肖像権への配慮が重視されている。これらの取り組みを適切に記録し、共有することは、デフスポーツやろう文化への理解を深める鍵となる。だからこそ、「伝えたい」と願うメディアやクリエイターの存在を尊重し、その実現を支える環境の整備を急がなければならない。そうでなければ、デフリンピックの魅力や価値は記録も発信もされないまま、社会に届かずに通り過ぎてしまうおそれがある。それは大会運営にとっても、レガシーを創出する貴重な機会を逸することにつながりかねない。
取材アクセスとは単なる「許可」ではなく、スポーツが社会とつながり、文化として共有されるための仕組みである。報道や記録は、共に未来を築く手段であり、それが積極的に奨励される大会であってほしい。
スポーツ基本法改正と「原点」の再確認
最後に、2024年6月13日・14年ぶりに改正されたスポーツ基本法では「人種、性別、年齢、障害の有無等にかかわらず」誰もがスポーツの楽しみを享受する権利が再確認された。また、パワハラやドーピングなどスポーツのあり方を見直す環境整備も盛り込まれた。
一方スポーツの現場では少子化・多様化に加え、東京2020での汚職事件のダメージによるスポーツ離れが加速してしまった。子どもの競技参加や地域スポーツの担い手不足、公共スポーツ施設の減少も起きている。
そのような中で「お金をかけない国際大会」として東京2025は、スポーツの持続可能性を問う機会となるだろう。ICSD(国際ろう者スポーツ委員会)が伝統的に当事者によるスリムな運営を行なってきたことは大会が長く続いてきた理由と言えるのかもしれない。
デフスポーツ観戦のインパクト、デフリンピックスクエアでの立場を超えた交流を通じて、ろう者とスポーツの文化が社会に浸透することを期待する。
プレスセミナーには多くの東京2020パラリンピック取材者が出席した。私たちには競技の魅力を伝えるとともに、「語られないまま終わるレガシーを作らない」責任がある。デフリンピック開催国として、“観る人・支える人・記録する人”それぞれの力を結集し、新しいデフリンピックを世界に提案できることが期待されている。

(写真取材・秋冨哲生 校正・中村和彦、そうとめよしえ)