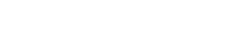東京2025デフリンピックが閉幕して約1ヶ月。街の喧騒は年末のそれへと移り変わったが、あの時、駒沢オリンピック公園陸上競技場に満ちていた「音のない熱気」は、まだ私たちの記憶に鮮明だ。大会期間中の11月19日、フィールドでは手話による「サインエール」が飛び交い、スタートランプの光が選手を導く。野村一路先生(元日本体育大学教授)に再会し、日本のスポーツ文化が抱える課題と未来についてお話を伺った。
デフリンピック・イヤーの締めくくりとして、野村先生の言葉を改めて振り返る。
「情報のアクセシビリティ」は万博の試金石になる
野村先生が駒沢を訪れていたのは、今後開催されるある国際博覧会(万博)に向けたプロポーザルのアドバイザーとして、デフリンピックにおけるICT活用や情報アクセシビリティの実例を確認するためだった。
「デフリンピックで実践されている『目に見える情報の伝え方』や現場のサポート体制は、将来の大規模な国際イベントでも重要なモデルになります」
先生はバレーボール会場の運営企業と共に、リアルタイムで動く現場の支援体制や情報伝達のあり方を熱心に視察していた。その眼差しは、この大会の知見を一過性のものにせず、地域や次の時代へ確実に継承しようとする研究者の真摯な思いだった。

「過剰な支援」は不要――デフスポーツ独自の文化
実際にスタンドで競技を目の当たりにした野村先生は、デフスポーツと、いわゆる「パラスポーツ」との決定的な違いについて語った。
「多くのデフアスリートは、普段は健聴者と一緒にスポーツをしています。車いすユーザーや視覚障害の方へのサポートより彼らが必要とする配慮は限定的です。『必要なサポートを、必要な分だけ』提供すれば、デフアスリートは自立して競技を楽しめるのです」
何でも手厚く支援することが正解ではない。その気づきに加え、野村先生は会場の空気感にも言及した。
「『サインエール(手話による応援)』が飛び交う独特の雰囲気も素晴らしい。手話は一つの言語であり、文化です。この『手話という言語が作る文化』が可視化されることは、多様性を理解する上で大きな意味があります」
「福祉の根っこ」が抱える、構造的課題
一方で、野村先生の視点は、日本のデフスポーツ運営が抱える構造的な課題を捉えていた。
「日本のデフスポーツ界は、スポーツ専門の団体ではなく『全日本ろうあ連盟』という福祉の領域から発展してきた独特の歴史があります。連盟の中にスポーツ委員会があり、その下に各競技団体がぶら下がっている。これは国際的に見ると非常に特殊な構造です」

野村先生はこの構造を、「福祉という太い幹から、スポーツという枝が伸びている状態」だと分析する。 この体制は、強力な組織力という「福祉の強み」を持つ反面、スポーツとしての専門性や国際連携においては課題も浮き彫りにした。
実際の取材現場でも、即時性が求められるリザルト(競技結果)の遅延や国際団体(ICSD)との情報連携の不備と垣間見える運営上の課題もみられた。先生は次なるステージへのステップとしてこう語る。
「それらは、スポーツとしての運営文化がまだ十分に徹底されていない証左かもしれません。行政の扱いも同様です。例えば一部の政令指定都市では、今回も2度にわたり国の法律(スポーツ基本法)が変わってもいまだにパラスポーツの管轄がスポーツ部局ではなく『福祉』管轄にあるケースも見られます」
スポーツを「お祭り」で終わらせないために
デフリンピックという大きな祭典を終えた今、日本はどう変わるべきなのか。野村先生の提言は、スポーツ行政の「革命」にまで及ぶ。
「今の日本のスポーツ行政は、専門家が少ない役所主導の限界に来ています。本来は、日本スポーツ協会(JSPO)やパラスポーツ協会が統合し、民間主導で専門性を持ちながら統括すべきです」
そして、インタビューの最後に語られたのは、先生が長年提唱し続けている「セラピューティック・レクリエーション(TR)」の思想だった。
「スポーツは人間が作り出す芸術作品です。大会期間中の『お祭り騒ぎ』だけで終わってはいけません。大切なのは、障害のあるなしに関わらず、その人が『生きる楽しみ』を取り戻し、主体的に人生を楽しめるようになることです」
野村先生は、これからのスポーツ文化のあり方を「庭園」に例えて語ってくれた。
「大会という華やかな『花束』を飾って終わりにするのではなく、誰もが好きな時に種をまき、自分なりの花(楽しみ)を咲かせられる豊かな『土壌(日常の庭園)』を作ること。それこそが、デフリンピックの真のレガシーなのです」
東京2020、そして東京2025デフリンピック。そのレガシーは、メダルの数ではなく、日常生活にどれだけ根づいたかで測られるべきだという。最終的に目指すのは、スポーツが特別なイベントではなく、生活の一部として自然に存在する社会である。

「文化」としてのスポーツへ
駒沢のスタンドでの学びと交流は、デフリンピックをただスポーツ大会としてではなく、日本社会の在り方を問い直すための鏡として映し出していた。
「スポーツは世界共通の人類の文化である」と法律に書かれているけれど、日本ではまだ本当の意味で文化になっていない。
今年11月の駒沢で野村先生が残した言葉は、素晴らしい大会を終えた今、さらに私たちに響く。東京2025デフリンピックをきっかけに、私たちの社会がスポーツを「福祉」という枠組みから解き放ち、誰もが当たり前に享受できる「日常の文化」へと昇華させられるかどうか、これからの歩みの一歩ずつがその試金石となるのかもしれない。
(写真取材・秋冨哲生)